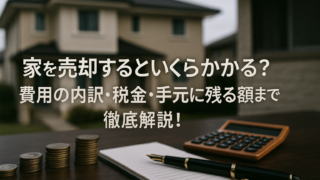不動産投資で節税は本当にできる?仕組み・注意点をわかりやすく解説
「不動産投資で節税ができるって本当?」
最近、SNSやYouTubeなどでもこうした話題を目にすることが増えました。
実際、不動産投資はうまく活用すれば、所得税や住民税の負担を軽減できる制度的なメリットがあります。
特に、減価償却や損益通算といった仕組みを理解して運用すれば、会社員や高年収の方にとっては大きな節税効果が期待できるでしょう。
しかし一方で、「節税になると思って始めたのに損をした」「結局お金が残らなかった」という失敗談もあとを絶ちません。
節税という言葉だけが独り歩きし、本質である投資のリターンや出口戦略が見落とされていることが、その原因です。
この記事では、不動産投資による節税の仕組み・注意点・年収別のシミュレーションまで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。
不動産投資で節税ができる仕組みとは?
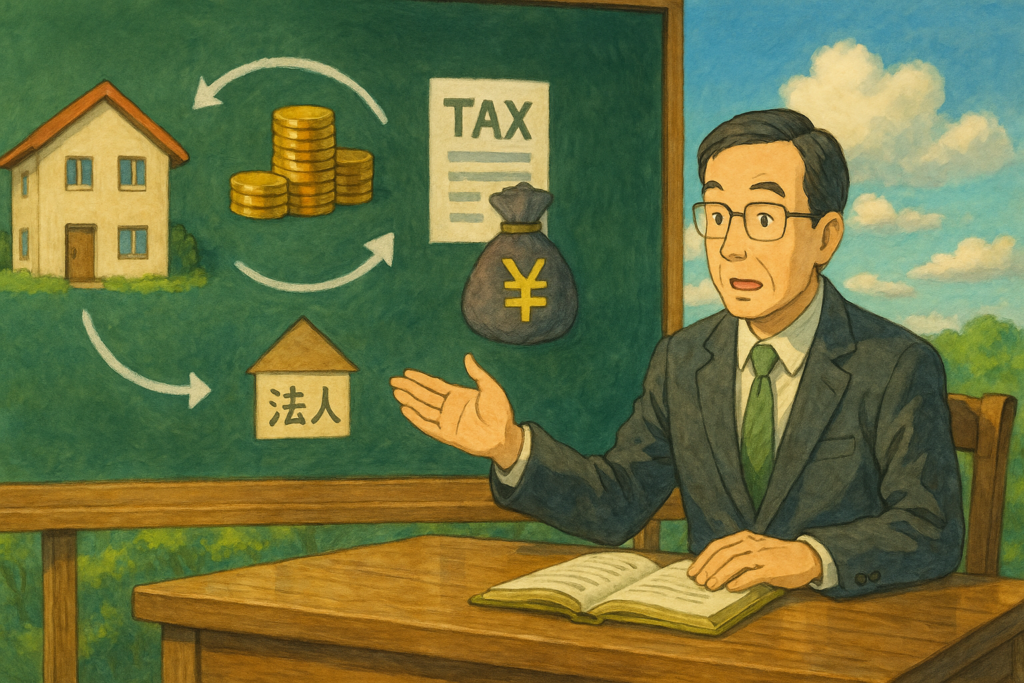
不動産投資は「節税目的でも活用できる」と言われることが多く、特に高所得者層や副業を考える会社員の間で注目されています。
その仕組みの根底にあるのが、「実際のキャッシュ(現金)」と「税務上の所得」のズレを利用できる点です。
具体的に課税所得を圧縮し、所得税や住民税の負担を軽減する方法を解説します。
減価償却による課税所得の圧縮
不動産のうち、建物や付属設備などは、時間の経過とともに価値が減少する資産として扱われます。
この価値の減少分を毎年少しずつ経費として計上できるのが「減価償却」です
。現金の支出が伴わずに経費が計上できるため、帳簿上の所得が圧縮され、結果として納税額が下がるというメリットがあります。
たとえば築25年の木造アパートであれば、耐用年数はわずか4〜5年と短く、大きな償却費を短期間で計上できます。
こうした点から、中古の木造物件は減価償却による節税効果が高いとされています。
仮に、建物価格1,600万円のワンルームマンションを購入し、耐用年数4年で減価償却した場合、毎年400万円の経費計上が可能です。
家賃収入が100万円でも、実費経費と合わせると帳簿上は赤字となり、給与所得と損益通算すれば大きな節税につながります。
ローン金利や諸経費の経費計上
さらに、不動産運用にかかる支出の多くは経費として認められています。
ローン利息や固定資産税、修繕費、管理費、さらには物件視察のための交通費なども含まれます。
ただし、ローン返済のうち元金部分は経費にできないため、帳簿上は赤字でもキャッシュが手元に残らないという状況が起こる点には注意が必要です。
損益通算による税負担の軽減
赤字になった不動産所得は、給与など他の所得と合算(損益通算)することができます。
これにより、全体の課税所得が減り、所得税や住民税が軽減されるのです。
ただし、損益通算には条件があり、確定申告が必要です。
また、マイホームの住宅ローン控除との併用や、一定以上の所得を持つ場合には制限がかかるケースもあるため、制度の正しい理解が求められます。
法人化による節税効果
個人よりも法人の方が節税面で有利な場合もあります。
法人化すれば、所得を家族に分散したり、広い範囲の経費(社宅、車両、役員報酬など)を活用したりと、税負担を抑える戦略が可能です。
また、赤字の繰越期間が10年と長く、柔軟な資金繰りにも役立ちます。
一方で、設立・維持にコストがかかる点や、住民税の均等割が発生する点、金融機関の融資姿勢が厳しくなる可能性もあるため、法人化には一定の検討が必要です。
サラリーマンが不動産投資で節税できるって本当?
年収600万・1000万・1500万で節税効果はどう変わる?
不動産投資による節税効果は、所得税率の違いによって大きく左右されます。
所得税は累進課税制度を採用しており、年収が高い人ほど税率も高くなるため、同じ金額を損益通算で控除しても、節税額には大きな差が生まれます。
不動産所得の赤字が年間100万円発生した場合に、年収別でどの程度節税になるかのシミュレーションです。
(※控除前課税所得が想定ベース、住民税10%を一律とした簡易計算)
| 年収 | 所得税率 | 住民税率 | 節税額(概算) |
|---|---|---|---|
| 600万円 | 約20% | 10% | 約30万円 |
| 1000万円 | 約33% | 10% | 約43万円 |
| 1500万円 | 約43% | 10% | 約53万円 |
つまり、同じ100万円の帳簿上の赤字でも、年収によって節税インパクトは数十万円変わることになります。
注意点
- 「赤字=現金が戻ってくる」ではない
- キャッシュフローがマイナスの場合は、税金は減ってもお金は減るリスクも
副業としての注意点(職業別の制限やバレるリスク)
不動産投資は一般的に「不労所得」または「資産運用」に位置づけられ、副業にあたらないと解釈されるケースが多いですが、会社の就業規則や業種によっては注意が必要です。
確定申告をすることで、住民税の額が変わるため、副業していることが会社にバレる可能性があります。
回避策:確定申告時に「住民税を自分で納付」と申請する
これにより、勤務先には不動産収入分の住民税が通知されなくなり、バレる可能性を抑えられます。
| 職種 | 副業規定の傾向 |
|---|---|
| 公務員 | 原則禁止(例外あり) |
| 医師・看護師 | 届出制が多く、副業可能 |
| 銀行員・大手企業 | 明文化されていないが事実上NGのケースあり |
| ベンチャー企業 | 容認している企業も多い |
不動産投資が「事業規模」にまで達すると(例:5棟10室超えなど)、「営利事業」と判断され、副業NGとなる可能性もあります。
公務員や医師でもできる?合法的な節税の条件とは
公務員でも不動産投資はできるのか?
公務員は副業が原則禁止とされていますが、「資産運用」としての不動産投資は、一定の条件下で認められることがあります。
ポイントは、投資が“事業的規模”に該当しないことと、勤務先に届け出を行っていることです。
具体的には次のような条件が目安になります。
- 5棟または10室未満の規模
- 物件の管理・運営を外部に委託しており、自身が実務を行っていない
- 所属庁などへの事前申請・許可を取得している
これらを満たせば、多くの場合「副業」ではなく「資産管理」とみなされ、公務員でも合法的に不動産投資を行うことが可能です。
医師・士業・国家資格職のケース
医師や税理士、行政書士などの国家資格職は、法律や就業規定の範囲内で一定の兼業が認められています。
業務との利益相反がなく、かつ公的機関や勤務先の規則に反しない形であれば、不動産投資も節税手段として十分に活用できます。
ただし、医療法人の代表や税理士法人の役員など、特定の立場にある場合は制限が設けられていることもあるため、事前に法人の定款や契約内容を確認しておくのが安心です。
不動産投資による節税は、会社員や自営業者だけでなく、規制の多い職業の人にも活用の余地があります。
ただし、職業ごとにルールや制限が異なるため、「できるかどうか」ではなく、「どうすれば合法的にできるか」を考えることが大切です。
節税を目的にするのではなく、あくまで長期的な資産形成の一環として位置づけること。
その上で、節税というメリットを副次的に活かす姿勢が、成功する不動産投資の基本です。
不動産投資の節税は「嘘」「失敗」と言われる理由

「不動産投資で節税できる」というのは事実です。
しかし、実際に始めてみると「思ったより節税にならなかった」「節税はできたけど、結局損をした」と感じる人も少なくありません。
多くの場合、これは節税の仕組みを十分に理解しないまま投資を始めてしまったことが原因です。
ここでは、不動産投資で失敗とされがちな節税の落とし穴について解説します。
節税になるのは最初だけ?仕組みの“落とし穴”
不動産投資による節税の中心は減価償却です。
この効果は強力ですが、物件の耐用年数を過ぎれば償却は終わり、税務上の経費としては使えなくなります。
たとえば、耐用年数4年の中古物件なら、5年目からは減価償却がゼロ。節税できる余地はなくなり、課税所得がそのまま税金計算の対象になります。
ポイント
- 節税効果は初年度〜数年に集中しやすい
- 償却終了後は税負担が急増する
- 長期保有に向かない物件もある
キャッシュフローがマイナスでも税金は戻るのか?
帳簿上は赤字になっていても、手元にお金が残っていないケースは多々あります。
減価償却によって「見かけの赤字」は作れても、ローン元本の返済や管理費などの支出は現実に発生します。
「節税で税金が減ったのに、通帳残高は増えていない」というのは、キャッシュフローと損益の違いによるものです。
ポイント
- 節税効果は初年度〜数年に集中しやすい
- 償却終了後は税負担が急増する
- 長期保有に向かない物件もある
売却時の譲渡所得課税で損をするケース
不動産投資で節税できたとしても、最後に損をすることがあります。
特に見落とされがちなのが「物件の売却時」。利益が出た場合は譲渡所得税が発生します。
しかも、保有期間が5年以下だと課税率は約39%。減価償却で取得価格が下がっているぶん、課税対象となる譲渡益は増え、税額も大きくなります。
ポイント
- 譲渡益に最大約40%課税される
- 減価償却分が課税額を押し上げる
- 売却前に必ず税額をシミュレーションすべき
このように、節税できるからといって安易に飛びつくのは非常に危険です。
本当の意味で「得をする投資」にするためには、税務の知識と出口戦略の両方を持っておくことが欠かせません。
【シミュレーション】不動産投資の節税効果はどれくらい?
「実際どのくらい節税になるのか?」という疑問は、不動産投資を検討する誰もが気になるポイントです。
ここでは年収別のケーススタディ、新築・中古や物件規模による違い、さらに自分でも試算できるExcelシミュレーションの方法を紹介します。
年収別シミュレーション(600万/1000万/1500万)
不動産投資による節税効果は、主に損益通算で得られる「所得控除」によるものです。年収が高いほど税率が高くなるため、同じ赤字額でも年収が高い人ほど節税額が大きくなります。
以下は、年収別に「不動産所得の赤字が100万円出た」場合の節税効果の目安です。
| 年収 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 | 節税額(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 約20% | 10% | 30% | 約30万円 |
| 1000万円 | 約33% | 10% | 43% | 約43万円 |
| 1500万円 | 約43% | 10% | 53% | 約53万円 |
※あくまで概算。実際の控除額や扶養の有無により変動します。
このシミュレーションから言えること
- 高年収層ほど節税効果は大きい
- 赤字額が同じでも、税率の差で節税額に20万円以上の差が出る
新築vs中古、ワンルームvs一棟で節税効果はどう違う?
不動産の「種類」や「築年数」も節税効果に大きく影響します。特に注目すべきは、減価償却期間と経費の幅です。
■ 新築 vs 中古
| 項目 | 新築物件 | 中古物件 |
|---|---|---|
| 耐用年数 | 長い(22~47年) | 短い(4~15年程度) |
| 減価償却額 | 毎年少ない | 毎年大きい |
| 節税効果 | 少なめ・長期型 | 大きめ・短期集中型 |
→ 短期的に節税効果を狙うなら中古物件が有利です。
■ ワンルーム vs 一棟物件
| 項目 | ワンルーム | 一棟物件 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 少なめ(1,000万前後) | 多め(数千万〜) |
| 経費計上 | 限定的 | 範囲が広い(外構・屋根・共用部など) |
| 管理負担 | 小さい | 大きい |
| 節税可能性 | 小さい〜中程度 | 大きいがリスクも高い |
→ 初心者は中古ワンルーム、中〜上級者は一棟で節税+資産形成を狙うのが一般的です。
Excelでできる簡易的な節税シミュレーション方法
不動産投資における節税額を、ざっくり試算したい場合はExcelやGoogleスプレッドシートでの自作シミュレーターが便利です。以下は簡易的なモデルです。
■ 入力例(黄色が入力値)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間家賃収入 | 120万円 |
| 管理費・修繕費 | 30万円 |
| 減価償却費 | 80万円 |
| ローン利息 | 20万円 |
| 不動産所得の合計 | =収入 - 経費 = -10万円 |
→ ここで**−10万円の不動産所得(帳簿上の赤字)**が出る。
■ 損益通算による節税額計算式(例)
excelコピーする編集する= 赤字額 ×(所得税率+住民税率)
例:= -100000 × 0.43 (年収1000万円の人)
⇒ 43,000円の節税効果
■ シミュレーションのコツ
- 減価償却は「建物価格 ÷ 耐用年数」で毎年の額を算出
- ローンの返済は「利息部分」だけを経費に
- 管理費・固定資産税なども年ベースで概算可能
Excelでの試算は、購入前に「この物件でいくら節税になるか?」をイメージするのに非常に有効です。
慣れてきたら、複数年分・減価償却終了後の影響まで反映した中長期プランも作ってみましょう。
不動産投資で節税する際に押さえておくべき3つのポイント
不動産投資は節税効果が期待できる一方で、ただ「税金が安くなるから」といった短絡的な判断では思わぬ落とし穴にはまることもあります。
成功するためには、節税だけに目を向けるのではなく、税務・収支・出口までを見据えた戦略的な判断が不可欠です。
ここでは、不動産投資で節税を考える際に押さえておきたい3つの重要なポイントを解説します。
税理士の選定と相談タイミング
不動産投資は、所得税や住民税だけでなく、固定資産税・消費税・譲渡所得税など、さまざまな税金が絡みます。
そのため、最初から税理士に相談しておくことで、節税の制度や処理方法を正しく理解したうえで計画を立てることができます。
購入後になって「もっと早く相談しておけば…」と後悔するケースは少なくありません。
減価償却の初年度処理や青色申告の準備など、節税の効果を最大限に引き出すには事前の段取りが重要です。
短期で終わる相談ではなく、将来の法人化も視野に入れた中長期的な関係を築ける税理士を選びましょう。
節税と投資利益のバランスをとること
節税は投資判断の一部に過ぎません。減価償却で一時的に税金を減らせても、その分を上回る損失を出していては意味がありません。
例えば、赤字を出して節税できたとしても、空室が続けば家賃収入は減り、修繕費がかさめばキャッシュフローが悪化します。
節税ばかりを追いかけて収益性の低い物件を選んでしまえば、トータルでは損失につながります。
重要なのは、「節税+収益性+資産価値」すべてのバランスを取ることです。
ポイント:節税はあくまで“副次的メリット”と位置づける。
出口戦略(売却タイミングと税金の最適化)
不動産投資の利益は、運用中の家賃収入だけでなく、売却益(キャピタルゲイン)にも関わってきます。
このとき忘れてはいけないのが、「譲渡所得税」の存在です。
特に保有期間が5年以下だと、税率は約39%。5年を超えると約20%に下がるため、売却タイミングによって税額は大きく変わります。
また、減価償却によって帳簿上の取得価格が下がっているため、売却益が実際より大きく計算されることもあります。
売却を検討する際は、あらかじめ税額を試算したうえで、譲渡益の相殺方法(赤字物件との通算など)や相続対策も視野に入れましょう。
ポイント:5年超の保有で譲渡税を軽減。売却前に税額を試算する。
これらの3つのポイントを正しく押さえておけば、不動産投資を節税だけでなく資産形成にもつなげることができます。
一時的な税制メリットにとらわれず、長期的な視野と計画性を持って取り組むことが、成功への最短ルートです。
よくある質問(Q&A)
不動産投資による節税について調べていると、誰もが一度は疑問に思う点がいくつかあります。
ここでは、実際に検索されることの多い「節税に関する代表的な質問」にお答えします。
-
不動産投資は節税になりますか?
-
はい、一定の条件を満たすことで不動産投資は節税につながります。
具体的には、減価償却費やローン利息、管理費などを経費として計上することで、不動産所得を意図的に赤字にし、その赤字を給与所得と損益通算することで課税所得を圧縮できます。
-
不動産投資は節税になりますか?
-
はい、一定の条件を満たすことで不動産投資は節税につながります。
具体的には、減価償却費やローン利息、管理費などを経費として計上することで、不動産所得を意図的に赤字にし、その赤字を給与所得と損益通算することで課税所得を圧縮できます。
-
節税効果があるのは最初の数年だけですか?
-
基本的に「はい」と言わざるを得ません。
不動産投資における節税の中心は、減価償却による所得圧縮です。建物部分の価値は年数をかけて徐々に償却されていきますが、法定耐用年数を超えてしまえば、その分の減価償却は行えなくなります。特に、築古の中古物件を購入して短期間で減価償却を済ませた場合、4〜5年後には節税効果が消える可能性があります。
したがって、初年度〜数年での節税を前提に投資を行うのであれば、その後の収支バランスまでシミュレーションしておくことが大切です。
-
節税効果があるのは最初の数年だけですか?
-
基本的に「はい」と言わざるを得ません。
不動産投資における節税の中心は、減価償却による所得圧縮です。
建物部分の価値は年数をかけて徐々に償却されていきますが、法定耐用年数を超えてしまえば、その分の減価償却は行えなくなります。特に、築古の中古物件を購入して短期間で減価償却を済ませた場合、4〜5年後には節税効果が消える可能性があります。したがって、初年度〜数年での節税を前提に投資を行うのであれば、その後の収支バランスまでシミュレーションしておくことが大切です。
-
不動産投資は元が取れるまで何年かかりますか?
-
この問いには明確な答えはありません。
なぜなら、「元を取る」という概念が、家賃収入によるキャッシュフローなのか、物件の売却によるキャピタルゲインなのかで意味が変わってくるからです。たとえば、家賃収入でローン返済と諸経費をまかないながら利益を出すには、10〜20年単位の長期保有が一般的です。一方、相場上昇に伴い早期売却で利益を得る「短期回収型」の投資もありますが、これは一部のケースに限られ、再現性は高くありません。
安易に「何年で元が取れるか」だけを基準に考えるのではなく、毎年の収支・節税効果・将来の売却戦略までトータルで見ることが重要です。
-
不動産投資がダメな理由は何ですか?
-
「不動産投資=ダメ」という評価は、間違った理解や不適切な投資判断から生まれることが多いです。
実際にうまくいかない理由の多くは、以下のようなケースに起因しています。一つは、節税目的で購入したものの、キャッシュフローが赤字続きで資金繰りが厳しくなるパターン。帳簿上は赤字で節税ができても、ローンの元本返済や修繕費で実際の出費が大きく、資金が残らないことがあります。
また、節税できるからといって収益性の低い物件を高値で買わされる例も少なくありません。特に、営業マンの「節税になりますよ」というセールストークを鵜呑みにして契約すると、売却時に大きな損失が出ることもあります。
不動産投資がダメなのではなく、適切な知識と判断材料を持たずに始めることが危険なのです。
【まとめ不動産】不動産投資による節税は「目的」ではなく「手段」として活用しよう
不動産投資による節税はたしかに魅力的ですが、節税だけを目的に投資を始めるのはリスクが高いです。
本来は、安定した家賃収入と資産形成を目指す中で、税金対策は「手段」にすぎません。
自身の年収や資産背景に合った投資計画を立て、必要に応じて税理士にも相談しながら、堅実に資産を増やしていきましょう。